写真家の眼と感性で捉えた都市の
表情や姿を紹介していく
大林組のカレンダーシリーズ
「CITYSCAPES」。
本サイトでは、カレンダーを撮影した
写真家とその作品にフォーカス。
作家にとって都市とはどのような
存在なのか、その思いに迫ります。

金本 凜太朗
Rintaro Kanemoto
2025年版カレンダーは
「Still Life(静物)」です。
独得の距離感から
被写体を見つめる作品は、
その静かなたたずまいの中に
都市のさまざまな物語を包み込み、
都市の息づかいを伝えます。

直線と曲線が混沌と
混じりあった
都市の中から
都市はあまりにも圧倒的で
東京に暮らしている以上、これまでも都市にカメラを向けることは度々ありましたが、今回「CITYSCAPES」というテーマをいただき、あらためて都市と向きあってみました。
都市はあまりにも大きく、そこに存在する人も車もストーリーもあまりにも膨大すぎて、とてもじゃないけれど「理解不能」、とてもじゃないけれど「かなわない」と思わされてしまいます。そもそもこれが人間の手でつくられているということ自体、いまだに信じられない気がします。

都市は直線と曲線からなっている
とはいうものの、高いところから眺めた都市は遠くなればなるほど要素が整理され、圧縮されて直線の世界になっていくように感じます。それはまるで定規やコンパスなど道具を使って描いた幾何的な景色のようでもあり、動きのない静物画のようでもあります。
ところが近いところ、例えば展望台なら、すぐ下の景色に目を凝らせば、ひしめき合い、動きつづけながら日々を営む人たちがいます。こちらはフリーハンドで描いたような曲線の世界です。
そこで今回は、直線と曲線、この2つの要素が混ざり合ってできている都市を、いちばん俯瞰できる展望台から撮ってみることにしました。展望台はよく通っていて馴染みのある場所。そこからあらためて都市を見てみたくなりました。
宇宙人的な視点で都市を見つめて
展望台から眺める都市は音もなければ匂いもありません。喧騒から逃れられるせいでしょうか、現実世界というよりも音をミュートした高精細なテレビ画面を見ているようで、不思議と落ち着ける場所でもあります。
そう思うのはこの関わり方が自分にとっていちばん心地よいからなのでしょう。
俯瞰できる位置というのは、ある意味でお互いに干渉せずにいられる距離感があるということであり、それは直接的なコミュニケーションが発生しない状況です。言い換えれば、ちょっと部外者的、宇宙人的な視点から都市を眺めているような感じがあります。
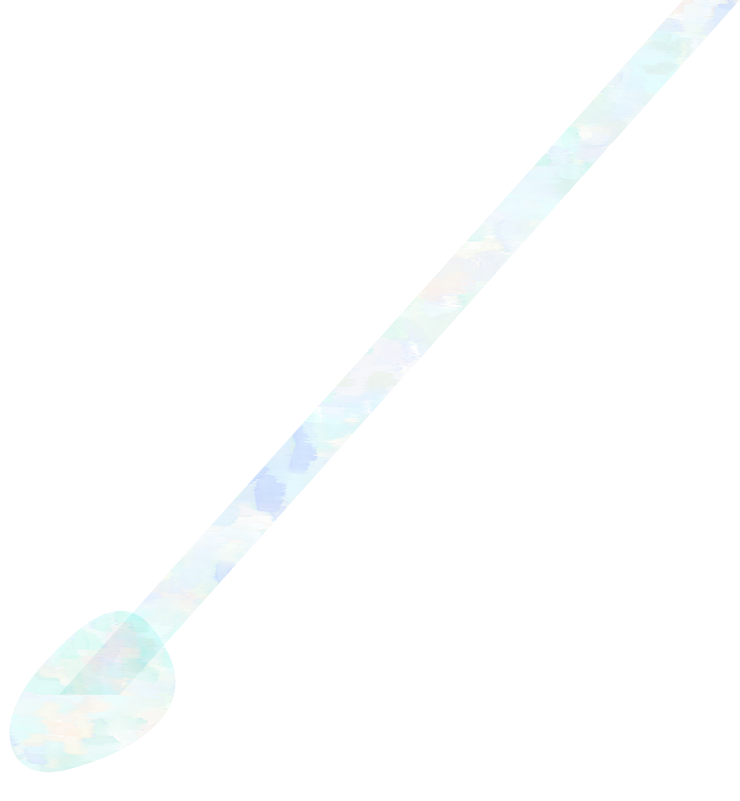


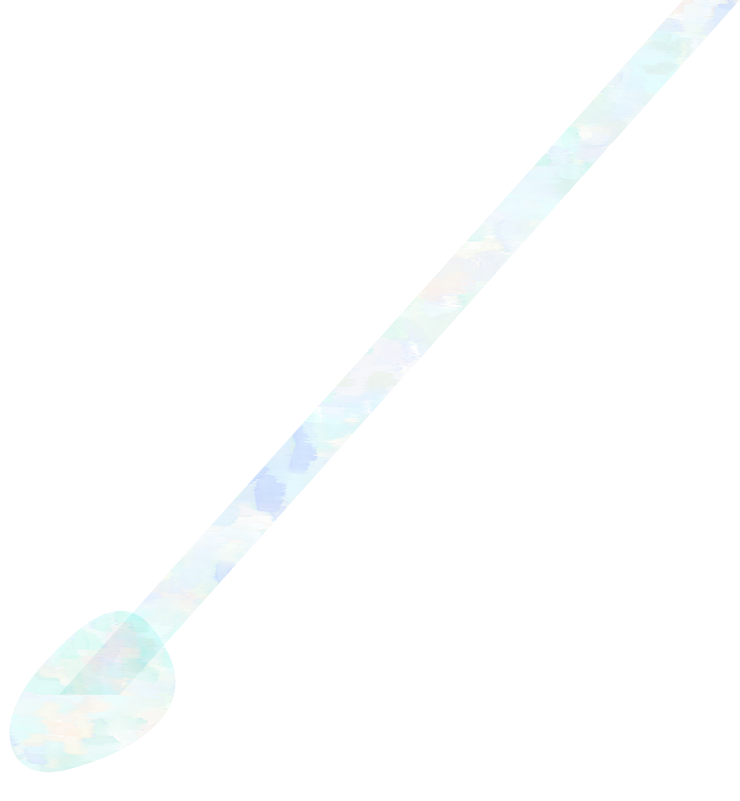



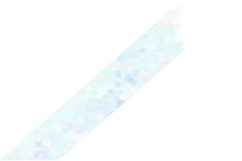

レンズを介した世界は
驚きや発見に満ちている
鳥とプランクトンを眺めていたように
展望台でカメラを手にしていると、顕微鏡でプレパラートの中でうごめくプランクトンを観察していた小学生の頃の自分とどこか重なるような気がします。
理科の授業がきっかけで顕微鏡にものすごく興味を持つようになりました。田んぼで採取してきた水を1週間くらい放置しておいて顕微鏡で覗くんです。すると色々な微生物が見えるんですね。それが面白くてしょうがなかった。毎日飽きもせず延々と観察していました。
もうひとつ、顕微鏡よりも前からはまっていたのが鳥を見ることでした。休み時間になると友達と2人、校庭の遊具の上に寝そべって鳥を探して空を眺めていました。そのうちに日本野鳥の会が主催する探鳥会にも参加するようになって、双眼鏡で鳥を探すようになりました。
考えてみると、ミクロとマクロの差はあっても、どちらも遠くのなにかを眺め、観察しているわけで、それがとにかく好きだったのだと思います。
気になったら、なにはともあれカメラを向けて
小学5年生の頃、母のお下がりのコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)をもらってからは、なにかを見つけるたびに記録するようになりました。双眼鏡で鳥を見つけたら写真に撮る、顕微鏡でなにかがいたらカメラを顕微鏡にくっつけて撮影する、というように。当時は、「これがいたんだよ」「これ、見たよ」と証明したり、後から図鑑で調べたりするための記録でしかありませんでした。
お年玉をはたいて一眼レフを買ってからは、カメラそのものにも興味が湧き始めました。鳥の写真を撮ってはインスタグラムに投稿していましたし、母がつくってくれた夕食やおやつ、電線と空、道ばたの草花など、日常のあらゆる気になるものに手当たり次第にカメラを向けるようになっていきました。

なにかを介して見るという行為に惹かれて
双眼鏡も顕微鏡もレンズを介して増幅するツールです。鳥は双眼鏡がないと近寄れないし、微生物も顕微鏡がないと見ることができません。見たいものに近づくためにはツールを介さなければならないし、間にレンズがあるのは顕微鏡も双眼鏡もカメラも同じです。今思うと「なにかを介して物を見る」こと自体に惹かれたのかもしれません。
距離感やテクスチャーを変えることで肉眼とはまた違う驚きや発見があることに好奇心を刺激されるのは今も昔も変わりません。微生物も鳥も都市も同じこと、ただなにをどんなスケールで見ているのか、だけが違っているような気がします。


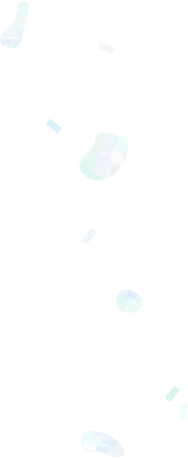
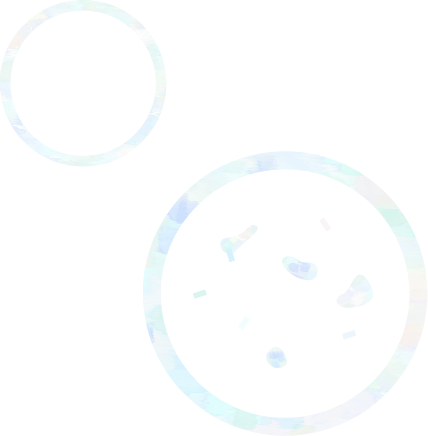


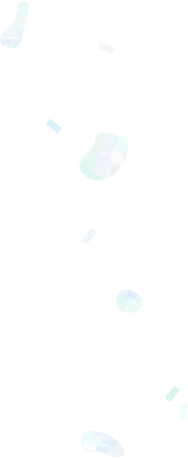
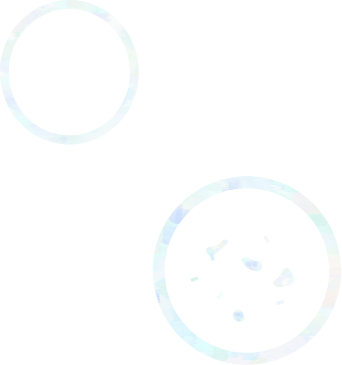


展望台から眺め、
ズームし、
フレームに収める
撮りたいものはその日、
その瞬間で変化して
今回は、まずは場所選びをしようと東京や大阪、名古屋など都市を巡っては展望台に昇りまくり、候補を絞り込みました。新鮮な感覚のまま撮りきってしまいたいので、撮影はひとつの展望台につき1回を基本にしています。
そうやってカメラを構えるのですが、目に入ってくるものは日によって変わる気がします。気になる色やかたちが違うこともあれば、飛び込んでくる量自体が異なるように感じることもあります。どこででも同じように見ているはずなのですが、撮るに至るまでのきっかけが少ない日と多い日があるということなのかもしれませんし、自分の感情や気持ちが影響を与えているのだとも思います。とはいえ、なぜ違ってくるのか、ちょっと不思議な気もしています。

ズームして初めてわかることもある
撮影では、場所を決めたらとにかく何時間も肉眼でひたすら眺めます。そうして気になるものがあったらカメラを手にとりズームします。とはいえ、ズームするまでは何が気になったのか自分でもわからないことも多いのです。なんといってもかなり遠くから眺めているので。
例えば大阪で日没近くに「あべのハルカス」に昇った時は、遠くに見えた細い線に気がつきました。スーッと真直ぐに伸びている光の線で、肉眼では正体がわからないけれど変な違和感があったんです。「何だろう」と思いながらカメラを向け、ズームしていくと商店街がありました。
これが今回のカレンダーで、いちばんズームした作品になりました。
ズームしてみて初めて面白さがわかることもけっこうあるので、気になったらとにかくズームして、片っ端から拾っていくように撮っています。
フレームに写りこむものを待ちながら
常に意識しているのは、「フレームにどんなものが写りこむか」。建築物をベースにフレームを想定しながら、要素としてなにを加え、なにを引いていくのかを考えながら撮影しています。例えば色や要素が欲しくて、建築物の後ろを車が通りすぎていく瞬間を狙ったり、人がいてほしいと思う場所に誰かが来るのを期待したりすることもあります。「なにか入ってこないかな」と漠然と待っていることも多いです。
逆に、撮影時には気づいていなかったものを後で発見することもあります。写真の片隅に人がポツンと写りこんでいたのが、思いもしなかったポイントになるとか。ビルの屋上の水盤の青さに惹かれてカメラを向けたら、その下のフロアでイベントが開催されていて、人の流れが不思議なレイヤーを生みだしていたとか。偶発的な要素には本当に驚かされます。
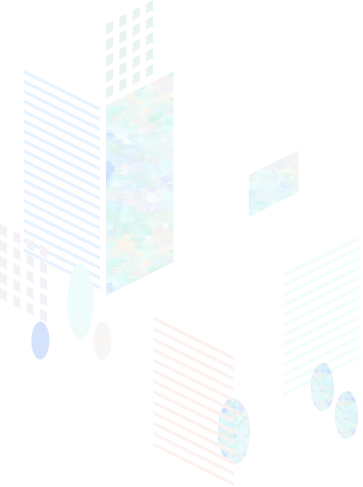
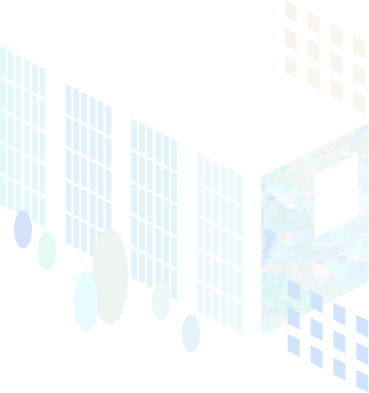

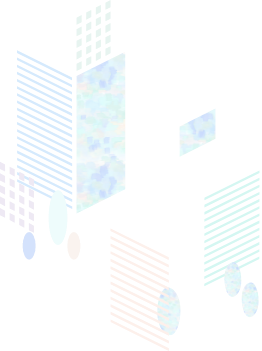
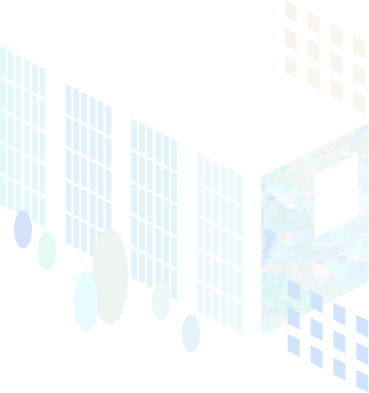



俯瞰して見えてきた
さまざまな都市の表情

見る人が解釈できる余白を撮りたい
僕は、写真自体にストーリーをあまり持たせたくありません。それよりも造形の美しさや、直線と曲線のバランスなど、自分なりの気持ちよさで構成したいと考えています。そこにどんなストーリーがあるかは、見た人がその人なりに感じてもらいたいし、人によって感じ方が違ってくるような、解釈の「余白」がある写真になってくれたらと思いながら撮っています。
特に今回はカレンダーのための撮影で、1枚の写真が2カ月も同じ空間に存在し続け、毎日のように目にするタイプの作品です。だとすれば、視点も気分もその度に違うし、気になることも変わるはずです。ある日眺めていて「あ、ここにこんな人がいたんだね」「この先になにかあるみたい」と気づいてくれるような、そういう要素をそっとちりばめておきたいと考えながら撮りました。


手掛かりとなる要素は少しだけ
一方で、その人がなにかを感じとるきっかけになる要素として、場所がわかるような情報もさりげなく写真の中に取り入れるようにしました。例えば渋谷ではスクランブル交差点を、神戸では港があることを伝えるために海を構成要素として組み込みました。
もうひとつ、常に意識しているのがトリミングです。仕事となるとその都度比率は変わってきますので、その中にどんな要素を入れるのか、特に枠ギリギリのところになにを持ってくるのかは毎回大きなポイントになっています。フレームの隅にいる人がどこに向かっているかは、その先への広がりを感じさせてくれますし、差し色が奥行きにつながることもあります。トリミングの小さな差で写真そのものが大きく変わってくることもあり、とても大切にしている作業でもあります。
この先も展望台から都市を捉えて
卒業後、フリーのカメラマンとして活動を始めてからは、新しいテーマを与えていただくたびに自分の視野が広がっていくように感じています。自分の選択肢になかった場所に行ってみたり、考えてもいなかった手掛かりが見つかったり、その一つひとつが僕の視点を広げてくれているように感じています。
都市をテーマにした撮影は本当に楽しかったです。ひたすら高いところへ昇って眺めて、を繰り返すうちに、場所によって支配する空気がまったく変わってくることを体感しました。空気が軽いところもあれば、想像以上にノイジーなところもありました。オフィス街なのにすごく爽やかなところもありました。
見れば見るほど、他の都市はどうなのか確かめてみたくなりました。どうやら展望台シリーズは、僕のライフワークのひとつに加わることになりそうです。

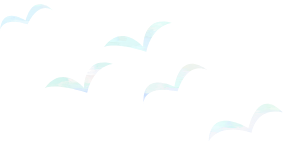




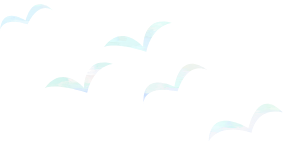






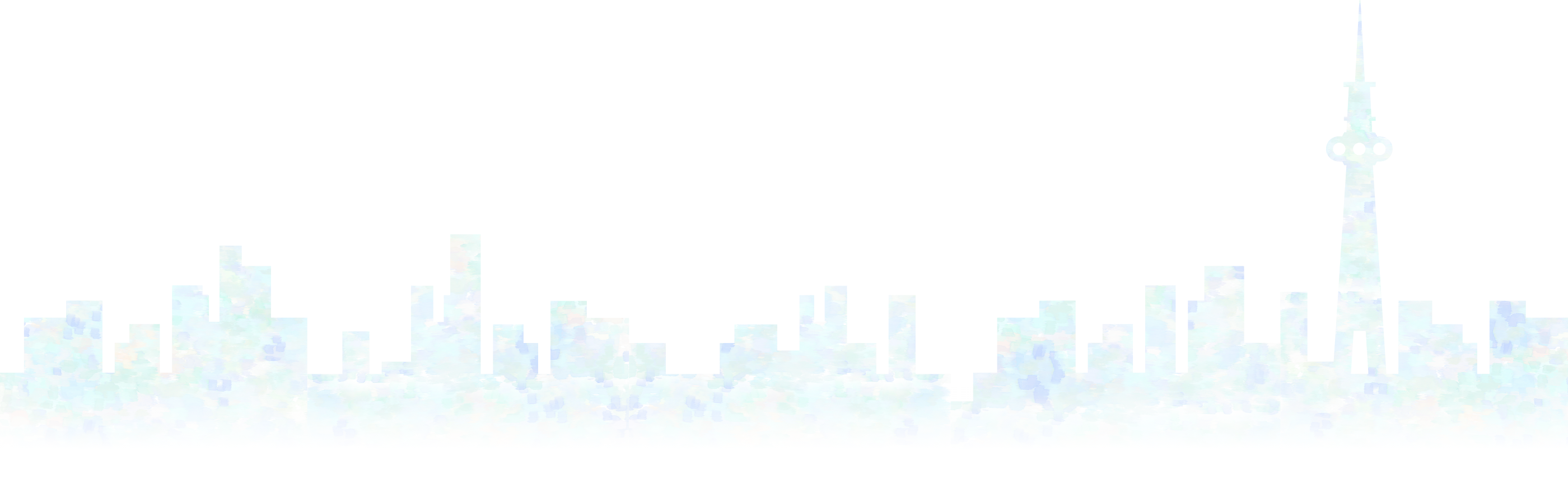
金本 凜太朗
Rintaro Kanemoto
1998年 広島県広島市生まれ。2020年東京綜合写真専門学校卒業、その後東京を拠点にフリーランスとして活動を開始。雑誌・WEB・広告などジャンルを問わず撮影を手掛ける。2024年開催の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024」では、公式カメラマンを担当。
【展覧会歴】
2017年個展 「North America」 Cafe Bresson(広島)。2020年グループ展 「a very personal record」 EBISU ROOM(東京)、個展 「5hoursYoyogi」 No.(東京)。2021年個展 「breath」 ギャラリー千年(東京)。2022年個展 「neighborhood」広島T-SITE(広島)。2024年個展 「A SKI RESORT」POMPONCAKES GARE(神奈川)、個展 「Language」CO-CO PHOTO SALON(東京)、個展「Still Life」THE BRIDGE(大阪)。
- 金本凜太朗 webサイト
- https://rintarokanemoto.com/
- 金本凜太朗 インスタグラム
- https://www.instagram.com/torintaro/




















