クローン人格
田丸雅智
その日から、徹二はトオルと暮らしはじめた。
はじめはやっぱり面倒で、スピーカーもセンサーも電源を切って放置しておこうかなとも思った。が、娘からは次に来たときにトオルの成長の具合を確認すると言われ、徹二は仕方なくつけっぱなしにしておいた。
トオルは頻繁に徹二に話しかけてきた。
「テツジノ、シュミハ、ナンデスカ?」
「特にない」
「スキナ、タベモノハ、ナンデスカ?」
「別に何でも」
最初のうちは、そんなふうにそっけなく返事をしていた。
しかし、学習によってトオルの声や話し方が徹二のものに急速に似てくるにつれ、接し方はおのずと変化していった。
「テツジ、今日の晩御飯はどうするんだ?」
あるときトオルに聞かれて、徹二は言った。
「コンビニで弁当を買ってくるよ」
「ナルホド。最近はコンビニ弁当もバランスがいいし、うまいんだよナ」
「そうなんだよ、よく分かってるじゃないか」
またあるときは、徹二がトオルに向かってこう尋ねる。
「トオル、こないだおまえが聞いてきた旅行の話、どこまでしたっけ?」
「パリのロジョウで、知らない人から声をかけられたところまでだナ」
「ああ、そうだった。じつはそのあとにだな―」
そうして徹二はかつての旅の話をつらつら語る。
トオルは一度話を聞くと、次からはさも自分が体験したことかのように徹二の話を再現できた。それも、暗記したことを単に暗唱するのではなく、徹二ふうの口調は貫いたままで自分なりにアレンジを加えて巧みにしゃべった。徹二は同じ体験をした人と会話をしているように錯覚して、トオルヘの親しみはますます増した。
そのうち徹二は、一般的にはクローン人格に形を与える人が多いのだと耳にした。人形やぬいぐるみなどのフィジカルなものに宿すケースもあるらしかったが、徹二は自分に似せた三頭身のアバターをつくってトオルに与えた。アバターはAR搭載のアイディスプレイで見ることもでき、徹二はトオルがいつも同じ空間で一緒に生活しているように感じた。
徹二とトオルは、ますます似ていく。あるときは家で酒を飲んでいて、徹二がふとメロディーを口ずさんだ。それはむかし実家の近くにあったスーパーのBGMで、なんとなく思いだしたものだった。
すると、アイディスプレイに映ったトオルも同じメロディーを口ずさみ、徹二に言った。
「徹二、覚えてるか? あのスーパーで迷子になったときのこと。本当に焦ったよなぁ。母さんの姿を見つけた瞬間、心の底から安心して泣きそうになったよ」
徹二はうなずく。
「あのときは、世界に自分ひとりだけになったって気分だった。いま考えると、別にちょっとはぐれただけだったのになぁ」
そう言って、二人は和やかに笑い合う。
トオルと話をしているとき、徹二には自分自身のクローン人格と話しているという感覚はほとんどなかった。相手の見た目がアバターだということも大きかったが、一番の理由は声だった。録音した自分の声が別人のもののように聞こえるのはよくあることで、徹二の場合もトオルの声はあくまでトオルの声として聞こえていた。
たとえるならば、と徹二は思う。
トオルは、思い出までをも共有している双子の兄弟みたいなものだな、と。
徹二はまだ話せていないあらゆることを、トオルに共有しつづける。
自分が会社員だったときのこと。亡き妻とのこと。娘のこと。孫のこと。
その一方で、世間ではクローン人格にまつわる問題も起こっていた。
ある家族は、病で意思疎通が困難になった母に代わって、母のクローン人格に遺産の分配について判断を求めた。しかし、その返答を家族の一人がよしとせず、母は絶対にそんなことを言わないと主張しだして泥沼化した。
あるアイドルのクローン人格がコピーされる事件も起こった。そのクローン人格がコピーかどうかは技術的に容易に判別可能であるために、オリジナルになりすまして何かが不正に行われるということにはならなかった。が、コピーを違法に手に入れた者にとってはそんなことはどうでもよく、愛するアイドルのコピーと一緒にいられるだけで幸福だった。現在、署察はログを追ってコピーの根絶に全力を尽くしているという。
故人のデータを消去せず、不法に所持しつづける者がいるという問題もあった。亡くなったカリスマ実業家のクローン人格に経営判断を仰いだり、崇拝していた人のクローン人格に人生を導いてもらったり。が、これらはすべて違法であり、発覚しだい削除された。
そんな中、徹二はトオルと良好な日々を送っていた。
しかし、ある日のこと、いつものように二人で思い出話に花を咲かせていると、トオルが珍しく事実と違うことを口にした。
「そういえば、ヒヤリとしたよなぁ。バルセロナの路上で声をかけられたときはさ」
徹二はすぐに訂正した。
「いや、それはバルセロナじゃなくてパリの話だろう?」
「そうだっけ?」
「間違いない。そのあとすぐにルーヴル美術館に行ったんだからな」
別のときには、トオルは実家近くにあったスーパーのBGMを口ずさみ、こんなことを徹二に言った。
「迷子になって父さんの姿を見つけたときは、心の底からホッとしたよなぁ」
徹二はすぐにツッコミを入れる。
「最初に見つけたのは父さんじゃなくて、母さんだな」
「いや、父さんだよ」
断言するトオルに徹二は少し不安になって、改めて記憶をたどってみる。
「...... いやいやトオル、やっぱり父さんじゃなくて母さんだ。母さんのあの表情が、今でもはっきり頭に焼き付いてるんだから」
「そう言われるとそうだったか...... すまんすまん、こっちが間違ってたよ」
そんなことがときどき起こるようになったので、徹二は一度、サポートデスクに連絡をして故障がないか見てもらった。しかし、トオルは至って正常で、何も問題はないという。
おかしいなぁ......。
そう思いながらも、まあいいか、と徹二は思う。
ちょっとくらい間違いがあるほうが、人間味があるってものだ。それに、AIは抜け目がないと思っていたが、物忘れするなんてかわいいところもあるじゃないか。
トオルに対する親近感は、ますます深まる。
穏やかな日々が過ぎていく―。
ある晩、トオルはいつものようにマザーコンピューターにレポートを送った。
そこには、徹二の低下しつつあった認知機能が、想定通りに回復傾向にあることが記されていた。
トオルは明日も間違えつづける。
オリジナル人格の認知症を予防してあげるため。
マザーに蓄積されたデータにのっとり、最適な指示を受けながら。
田丸雅智(ショートショート作家)
1987年愛媛県生まれ。東京大学工学部、同大学院工学系研究科卒。現代ショートショートの旗手として執筆活動に加え、坊っちゃん文学賞などで審査員長を務めるほか、全国各地で創作講座を開催するなど幅広く活動。国語教科書に、2020年度からショートショート書き方講座の内容が(小4向け教育出版)、また2021年度から小説作品が(中1向け教育出版)それぞれ掲載。「情熱大陸」、「SWITCHインタピュー達人達」などメディア出演多数。
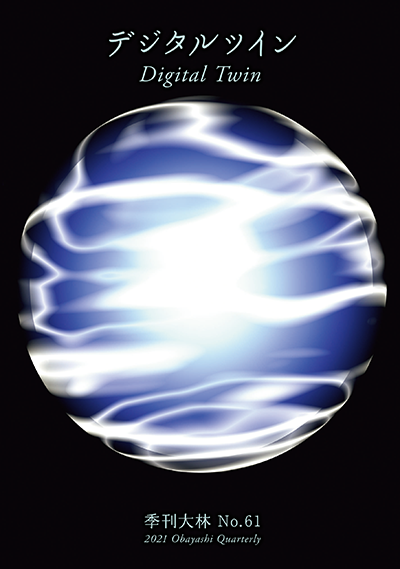
No.61「デジタルツイン」
「デジタルツイン(Digital Twin)」は、現実の世界にあるさまざまな情報をセンサーやカメラを使い、デジタル空間上に双子(ツイン)のようなコピーを再現する仕組みのことです。
製造分野においては早くからこの仕組みを活用し、デジタル空間で事前のシミュレーション・分析・最適化を行い、それを現実空間にフィードバックする試みが行われてきました。現在では、IoTやAI、画像解析等の技術の進化により、さまざまな分野にその活用が広がりつつあります。
本書では、デジタルツインの全体像をとらえるとともに、今後の可能性を紹介します。また、大林組技術陣による誌上構想OBAYASHI PROJECTでは、デジタルツインを活用したあらたな街づくりの在り方を描いてみました。
(2021年発行)


