シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15)
日本水準原点標庫
藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

(東京都千代田区永田町 憲政記念館庭園内)
写真提供:国土地理院
昔の地図は地面の形だけからできていたが、今はちがい、地形図には形に加え高さを示す等高線がくっきり描かれている。等高線があるから、道を通すにせよ河の流れをコントロールするにせよ、身近なところでは斜面に宅地を整備するにせよ、間違いなく実行することができる。
地形図の上で、等高線の段々を低いほうに下がってゆけば必ず最後は海抜ゼロの海岸線にいたり、高いほうに上がってゆけば、どっかの山の頂上にいたり、三角点の印と標高が記入されている。
以上のことは地形図を使ったことのある人ならだれでも知っているが、さてでは、その等高線の高さと三角点の標高はどうやって決めたのか、もっと具体的にはどこから測ってその高さを確定したのか。海岸まで出かけて海抜ゼロを決めようとしても、実際の海辺を思い出してもらえばいいが、波は寄せたり引いたり上がったり下がったりを繰り返し、どこが海抜ゼロなのか分からない。平気で1m以上の誤差が生まれてしまう。誤差をゼロに近づけるには、日本の国土のどこか一点を基準点として、そこから測量を全国展開するしかない。
この問題に初めて取り組んだのは、明治の陸軍の陸地測量部で、今の国土地理院の前身にあたる。明治24年、陸地測量部は、自分の属する陸軍省の前庭の一点を画して基準点とし、そこから24.5m下った位置にある油壷の海水面を海抜ゼロとした。そして以後、日本全国どこでも、この基準点から測った高さにより等高線を引き、標高を決めている。
日本の国土の高さを決める基準点のことを「水準原点」といい、今も、国会議事堂脇の旧陸軍省敷地跡に立つ憲政記念館の、庭の一画に存在する。

写真提供:国土地理院
半世紀近く前になるが、東京建築探偵団という活動をスタートさせた当初、明治期の建築文献を通して存在を知り、現場を訪れて、目を見張った。明治時代の標庫というから小さな煉瓦造の小屋との予想を大きく裏切り、石造のそれも古代ローマ神殿風の小建築が木陰に堂々と立っている。
近づくと、水平に走る石梁には右から左に向かって「大日本帝國」と浮き彫りがなされ、正面の壁には「水準原點」。今の日本で大日本帝国の5文字に出会うことはほぼないだろう。

写真提供:国土地理院
一呼吸してから、建物の作りをゆっくり眺める。こうしたヨーロッパの古代に範を採るスタイルをクラシック系といい、この建物が作られた明治初期には国の記念碑向きのスタイルとしての地位を確立していたから、設計者も採用したにちがいない。クラシック系にはギリシャとローマの二つの起源があり、これはどっちを基にしているのかを確かめる。
正面にペディメント(三角破風)の載るのはギリシャもローマも同じだが、列柱の回し方に差があり、ギリシャは四周に立ち並ぶが、ローマは正面だけ。様式の勘所をなす柱の上部の柱頭飾に着目すると、ギリシャはドーリア式、イオニア式、コリント式という三つの定型を持ち、ローマはそれに混合式と簡単なリングで済ます「トスカナ式」が加わる。
正面だけの列柱といい、トスカナ式の柱頭飾といいローマにちがいないが、どうしてギリシャではなくローマにしたのか。
古代ギリシャと古代ローマの建築の違いは、単純化すると"ギリシャの質とローマの量"に分かれ、ローマは世界を制覇するため、都市も建築も道路も水道も巨大化し、巨大化を支えるための標準化を旨として建設技術を発達させている。巨大化は建築より土木工事において著しく、土木工事の基礎的技術として測量が高度化していた。ローマ帝国は測量技術に支えられて繁栄していた。おそらく水準原点標庫の設計者は、そのことを強く意識してギリシャではなくローマのスタイルを採用し、あるいはさらに、ローマ帝国を思い浮かべながら大日本帝国の5文字を刻んでいたのかもしれない。

現場を訪れて"目を見張った"のは、この建物の設計者のことを、明治という時代をどう生きたかを知っていたことも大きい。佐立(さたち)七次郎という工部大学校の第1回卒業生で、他の3人の同級生(辰野金吾、片山東熊、曽禰達蔵)のように明治という進歩と拡張の時代を生涯かけて牽引することを途中で辞め、子孫の詩人金子光晴によると、「人との交渉を絶って、ひねくれ者として閑散無為な生涯を終わった」。「建設者たちの適者生存的な殺伐な気構えとテンポに、息切れしてついて歩けない、なにか気質なものがあると気づいて、手をうったとおもはれるふしがある」。
その佐立が、まだ元気に同級生と一緒に時代を牽引しようとしていた頃の堂々たる作がこの標庫なのである。

最後列4人のうち右端が辰野金吾、左から2人目が佐立七次郎
2列目左から4人目、佐立の前に立つのが片山東熊、1人おいて曽禰達蔵
- 現在のページ: 1ページ目
- 1 / 1
藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)
1946年生。東京大学大学院建築学専攻修了。主な建築作品に「ニラハウス」「高過庵」 「モザイクタイルミュージアム」、著書に『明治の東京計画』(岩波書店)、『建築探偵の冒険 東京編』(筑摩書房)、『藤森照信 建築が人にはたらきかけること』(平凡社)など。
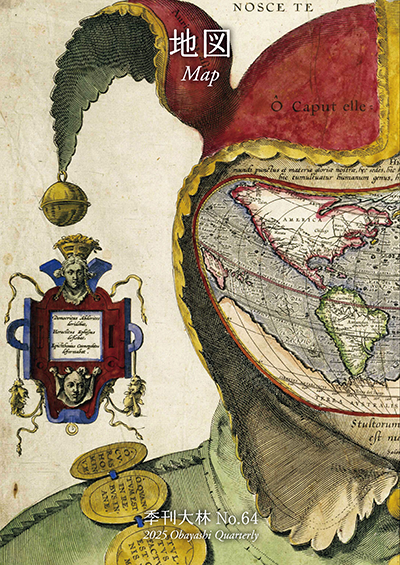
No.64「地図」
地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。
私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。
本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。
(2025年発行)
-
グラビア:これも地図?
- 全編を読む
-
地図とは何か
森田喬(法政大学名誉教授)
- 全編を読む
-
地図最前線―現在から未来へ
若林芳樹(東京都立大学名誉教授)
- 全編を読む
-
見えている世界、見えていない世界
大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)
- 全編を読む
-
地図を描く少年の夢と孤独
吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)
- 全編を読む
-
OBAYASHI PROJECT
本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く
想定復元:大林プロジェクトチーム
- 全編を読む
-
シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫
藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)
- 全編を読む
-
地図雑学
- 全編を読む


