見えている世界、見えていない世界
大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)
はじめに
イタリアの作家イタロ・カルヴィーノは、小説『見えない都市』(1972年)の中で、元国の皇帝フビライ・ハンに向かって西方の都市の様相を連日連夜にわたり語って聞かせる、旅行者マルコ・ポーロの姿を描いた(※1)。彼の語る都市の話は、虚実ないまぜになったホラ話とでもいうべき内容であるが、現実の都市はどうあれ、都市の姿を喚起していく「語り」、つまり「表現」のほうこそが、皇帝と、そして読者である我々の中に、世界認識を作り出していく。
※1 イタロ・カルヴィーノ著、米川良夫訳『見えない都市』河出書房新社、2003年
そんなマルコ・ポーロの語る都市の一つに、「水都エメラルディーナ」というものがある。そこでは人間たちが複雑に絡み合う水路と陸路を行き交う一方で、下水道を走る鼠や、屋根を歩きまわる猫、空中を縦横無尽に飛びまわる燕に至るまで、さまざまな生き物たちの通り道が形成されているという。そして、かような都市を描いた地図は、それらすべての道筋を含んでいなければならないはずでありましょう、とポーロは語る。当然、あらゆる道を描いた地図などというものはいまだかつて存在したことがないし、今後も存在することはないだろう。しかしながらこの挿話には、地図の描くべき対象は「見えている世界」に限らず、地底から空中まで、極小から極大まで、過去から未来に至るまで、「見えていない世界」すらも包みこんで、ほぼ無限に近いような可能性を含んでいるのだ、という鋭い示唆が含まれている。振り返ってみれば、普段わたしたちが目にするいかにも「正確だ」といわんばかりの地図も、世界のほんの一部しか表現できていないこととなる。
世界をありのままに描くことはできない。しかし、そんな無謀な目標に向かって、人類は実験を繰り返してきた。新たな主題を描くためには、新たな表現が必要となる。ここでは、「表現」という側面から地図の歴史を見直し、地図の限界を乗り越えようとしてきた人類の格闘の軌跡を追うことにしたい。

Berghaus, H. (1845). Physical Atlas (Physikalischer Atlas). David Rumsey Historical Map Collection.
地図の限界への挑戦──平面上の立体
地図というのは平面上に地球、つまり凹凸のある回転楕円体の一部を表現しなければならず、その時点できわめていい加減なものだと言わざるをえない。
地図表現の歴史は、平面上に立体物を正確に投影するための「投影法」の歴史であるとともに、地形の起伏を平面上に再現する「地形描写」の歴史といえよう。最初に考えられた地形描写の方法は、横や斜め上から見た山の姿を、真俯瞰の地図の上に強引にも描きこむ方法であった。そこには想像力に任せて描かれたイメージも含まれていたから正確なものとはいえなかったが、逆にいえば、知らない場所をそれらしく描く唯一の方法であった。絵画的な表現は豊かな地形喚起力を持ち、人々に旅行や探検への熱情を掻き立てたことだろうが、描かれた山の背後に隠れてしまう地物も多く、実用性という点では不満の残るものとなった。

De Saussure, H-B. (1779-96). Voyages dans les Alpes, Neuchatel: Fauche-Borel, 1779-96 (Source: BGE, Bibliothéque de Genéve).
絵画的な地形描写の欠点を解消するために現れたのが、「けば」表現(hachures)である。これは、線群の粗密と広がりによって斜面の立体感を作り出そうとする表現で、さきほどの絵画的描写に比べれば起伏の表現力に乏しいが、多くの欠点を乗り越えることができた。けば表現は長い間支配的な起伏の描写法となったが、リアリティという点では大きな疑問の余地を残した。

Hauptm. Rosenberg (gez.), Joseph List (gest.), Schlacht bey Zürich am 4 ten Juny 1799, Wien: gedruckt bei Anton Strauss, 1819 (Source: BGE).
やがて、太陽光を想定して山々に陰影をつける描写や、けばの太さに強弱をつけて陰影を表現する手法、実際に地形のレリーフを制作して照明を当て、写真に撮って地図として利用する方法などが開発された。精緻な銅版画技法と相俟って発展したこれらの描写法により、表現力や美しさといった観点からみれば、地形描写は19世紀後半から20世紀初頭に頂点に達したといえよう。

Collin, C. E. (ca. 1860). La rade de Naples et le Vésuve (Source: BGE).
その後、測量の発達に伴い、同じ標高の地点を線で結んだ「等高線」や、等高線で囲まれた区域を標高に対応した色で塗りつぶした「段彩」表現が実用化され、科学的に正確なものだとして受け入れられていったが、それだけでは満足いく立体感を知覚的に与えることはできず、線描や色彩による陰影表現などと組み合わせて複合的に表現されるのが一般的である。つまり、現在でも科学的な正確さと直感的表現力との間の葛藤は、解消されたとはいえない。
大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)
1981年生。武蔵野美術大学修士課程修了、芝浦工業大学博士課程単位取得退学。ダイアグラム・主題地図を中心とした情報視覚化の研究を行う。著書『世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』にて日本地図学会 学会賞(作品・出版賞)受賞。
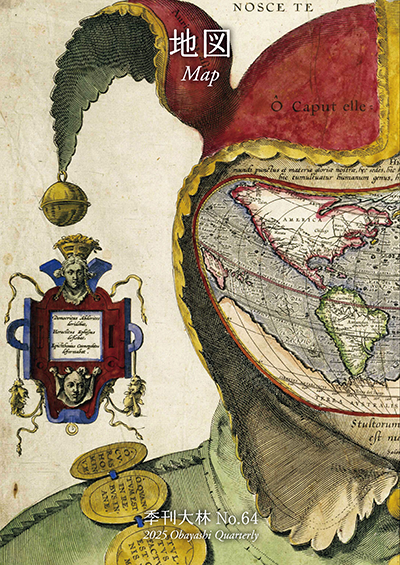
No.64「地図」
地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。
私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。
本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。
(2025年発行)
-
グラビア:これも地図?
- 全編を読む
-
地図とは何か
森田喬(法政大学名誉教授)
- 全編を読む
-
地図最前線―現在から未来へ
若林芳樹(東京都立大学名誉教授)
- 全編を読む
-
見えている世界、見えていない世界
大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)
- 全編を読む
-
地図を描く少年の夢と孤独
吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)
- 全編を読む
-
OBAYASHI PROJECT
本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く
想定復元:大林プロジェクトチーム
- 全編を読む
-
シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫
藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)
- 全編を読む
-
地図雑学
- 全編を読む


