地図とは何か
森田喬(法政大学名誉教授)
図面と地図
建設の分野は、図面や地図を多用する。しかし、その利用は当たり前すぎて、あらためて図的に表現するのがどういうことなのかといった議論はあまりされない。専門教育としては図学や製図法や測量学などを学ぶが、建造物や土地区画の形や寸法をいかに正確に表すかということが主眼である。しかし、計画や設計では図面を引きながら考えを進めるということも行われる。そして、その図面の描き方で思考の進み具合が違ってくる場合がある。これらの思考の展開に対して、「見れば分かる」ではなく視覚を使った思考の「方法」として議論することはあまり行われてこなかったのではないだろうか。
地図についての一般的なイメージには、「便利で面白い」という積極的な評価がある一方で「難しいし面倒くさい」というあまり歓迎されない見方もある。また、GPS利用が広まってきた時にもう地図は要らないという言い方が出てきたし、近年の自動運転の環境では利用者に地図は全く要らない。しかし、これらは予め決められた目的地に到達しようという道案内機能の場合であり、地図の多様な可能性にとってはごく一部でしかないことをまず確認しておきたい。
地図の種類は3Dである地球儀から始まって縮尺や目的に応じて様々なものが存在している。近年ではハザードマップや市街地の立体的なデジタルモデルも利用されるようになっている。これらで共通しているのは、目にしているのは対象物そのものではなく媒体上に表現された記号状の情報であり、そこからその意味として対象物を捉えていることである。このように何かに置きかえて伝えることは言語的な行いであり、地図に対しては地図言語という概念が存在している。地図は、紙に描かれたものからディスプレイ上のデジタル地図のようにダイナミックに変化するもの、さらには何かに置きかえる前の頭の中の空間イメージまで含めると実に様々な表れ方がある。あらためて地図とは何であろうか?その魅力を様々な角度より探ってみよう。
最古の地図?
世界で最も古い地図はいつ頃まで遡れるのであろうか?この問いかけは、人はいつ頃から言葉を話すようになったのだろうかということに等しく、分かっていない。しかし、物理的に地図のようなものが残されていることは知られている。動物の牙に描かれた山や川、洞窟の壁に描かれた火山と集落、岩に彫り込まれた集落、などが存在しているが、文字がまだない時代なのでそれが何を表すのかは確認できない。しかも、数千年の時間が経っているので描かれている空間と現在の実空間との照合は難しい。

約5000年前(新石器、青銅器時代)に氷河渓谷の岩に彫り込まれたもの。文字はまだない。
©Luca Giarelli / CC-BY-SA 3.0
また、容易に想像ができるのが、図のように地面に棒切れでひっかいて地図を描くようなことがあったのではないかということである。大きな空間において、川や道などを単純化し抽象化して線で表し、目標物を点で表すなどの記号化を通して構造理解を行ってきたとすれば、話し言葉と同様に、このような地図の言葉を利用することは人間の本性なのかもしれない。しかし残念ながら、そのようなものは残らない。

地図を描いてコミュニケーションを図っている。実世界、頭の中の空間イメージ、描く道具、描かれた地図、表現媒体、地図の説明、対話者で構成される。
我が国には8世紀頃に作成された東大寺開田図が現存している。ここには格子状の耕地割りが描かれているが、当時の律令制度の土地管理の方法が地図化されているものである。地図や図面では大きな空間を小さく縮めている。住宅の図面なら実寸大から100分の1程度で表すが、都市計画図は2,500分の1であり、国土地理院の地形図になると2万5,000分の1以上に縮めることになる。カメラのズームは数倍から数十倍程度であるから現物との対応関係が直観的に理解できるが、地形図では縮小率がそれより百倍や千倍も大きくなり、対応関係を把握するのは難しくなる。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)
上記の開田図は楮(こうぞ)紙上に描かれたものであるが、写生のように対象空間を観察しながら描いたのではない。描かれた全体がどのような構造、つまり部分と全体の関係性がどのようになっているのかを示すものとなっている。そして耕地割りは格子状で、位置関係が把握しやすくなっている。

現地がそれに基づいて造成されたとすると、この地図は計画図でもあり、また現地は実寸大地図のように展開している。そして、現地との照合のために山並みや樹木、池などが描き込まれているが、これも写生ではなく記号的な表現となっている。面白いのは池の中に魚らしい形が一つ描き込まれていることで、生き物は現地との照合のための目印にはならないからその意図は謎である。
あるいは、池を形と塗りつぶしだけで表すには不安が残り、魚を記号的に追加することにより念押しをしようとしたものなのかもしれない。
子どもと地図
言葉の利用には、言いたいことをどのように選び、それらをどのような配列により話すのかという構文論があり、さらに、そこで話した意味内容が思ったように伝わったのかという意味論による議論がある。地図も同様であり、言いたいことについてどのような地図記号に置きかえ、どのような配列で表現したのかということと、そのようにして表現された地図によって伝えたかったことがどの程度伝わったのかという評価の問題が生じる。そして、そこには親から教わる母国語と同様に、何らかの視覚表現の仕方の学習が求められるであろう。人は何歳ぐらいになったら地図が描けるようになるのだろうか?

図は小学4年生(10歳)が自宅付近の様子を描いたものである。用紙を前にして、自宅が自分に最も近い手前下の中央に描かれている。そこから情景が上に向かって自分から離れるように、小学校を経てさらによく利用する遊び場までが展開している。左手に縦に川、公園、池が配置されており、右手の端は道路で終わっている。気づくのは、描写されているものは全て記号的なイメージとなっており、例えば木の形は同じであり写生的ではないということである。しかし、木であることは明快に伝わり感じも悪くない。空間配置も実距離に比例しておらず伸び縮みさせて構造を単純化させている。生活や遊びと関係が深い動植物が記号的に丹念に記入されている。
一方、橋や駐車場など、形では表現しきれないものには言葉が記入されているが、これらは一般名詞であり、固有名詞である地名は全く見られない。また、描いていて用紙が足りなくなり上から3分の1程度を付け足している。予め全体が用紙に収まるように縮めるという発想は見られない。近代地図につきものの、縮尺、方位、地名、凡例などの縛りがなく、自分を中心に自由に近所の様子が表現されている。
子どもは小学5~6年生ぐらいから抽象思考ができるようになると言われている。つまり地図を頭の中で回転させて位置関係を把握し、相互距離を推察できるようになるが、上述の地図はそのような方位や縮尺の操作に左右されない自由な表現となっている。まさに子どもの地図であるが、しかし大人でも充分に了解可能なものとなっている。
近代以降の国が作成する地形図では、図法を定めることによりメトリック(※1)な機能と内容の均質性を獲得するが、一方でその縛りが個別的な空間認識に基づくイメージマップのような内容は受け付けない。このことが正確で信頼できるという地図の性善説を形作っている一方で、ユーザによってはイメージが湧かず興味が持てないものとなっているかもしれない。
※1 計測、測定基準。計測による一般的な地図をメトリックマップという
森田喬(法政大学名誉教授)
1946年生。早稲田大学理工学部、同大学院を経てフランス・パリ社会科学高等研究院博士課程修了(情報コミュニケーション科学博士)。元国際地図学協会(ICA)副会長、元日本地図学会会長、国際地図学会議2019年東京大会実行委員長。著書に『図の記号学視覚言語による情報の処理と伝達』(翻訳)、『神の眼鳥の眼蟻の目地図は自分さがしの夢空間』、『地図の事典』(編集代表)など。フランス芸術文化勲章受章。
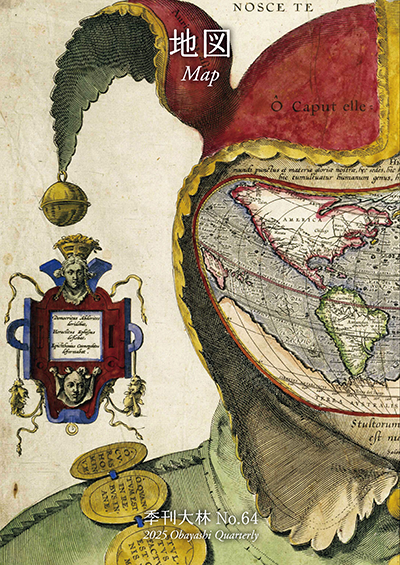
No.64「地図」
地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。
私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。
本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。
(2025年発行)
-
グラビア:これも地図?
- 全編を読む
-
地図とは何か
森田喬(法政大学名誉教授)
- 全編を読む
-
地図最前線―現在から未来へ
若林芳樹(東京都立大学名誉教授)
- 全編を読む
-
見えている世界、見えていない世界
大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)
- 全編を読む
-
地図を描く少年の夢と孤独
吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)
- 全編を読む
-
OBAYASHI PROJECT
本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く
想定復元:大林プロジェクトチーム
- 全編を読む
-
シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫
藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)
- 全編を読む
-
地図雑学
- 全編を読む


