ヘンリー・ダイアー(1848-1918)
エンジニア教育の創出
加藤詔士
お雇いスコットランド人教師
ヘンリー・ダイアーというお雇い教師がいる。英国をモデルに日本の工業化・近代化をめざした明治新政府が、スコットランドから招いた教師である。1873(明治6)年から82(明治15)年までの間、工学寮工学校とそれを継承した工部大学校(東京大学工学部の前身)の都検(教頭)ならびに土木学・機械学教師として、日本のエンジニア教育の組織化と実学人材の育成に貢献した。
クラークやベルツ、フェノロサほど知られていないが、彼らと違った興味深い活躍をした。日本でエンジニア教育を推進しただけでなく、その体験と成果を持ち帰り、郷里グラスゴーにおける教育実践の中に移し入れた。しかも、エンジニアをめざしてグラスゴー大学にやって来た日本人留学生を支援したのである。
エンジニア教育の新機軸
ダイアーは、鋳物工場での徒弟修業と技術カレッジの夜間課程を経て、グラスゴー大学に進みW・J・M・ランキン教授の指導を受けた。1872(明治5)年8月、岩倉使節団が英国を訪問したとき、副使の伊藤博文がランキン教授に人選を依頼。推挙されて日本に招聘されることになった。このような経歴と、J・S・ラッセル著『英国人のための体系的な技術教育』(1869)などを活用したヨーロッパの技術教育についての研究をもとに、あたらしい工学教育を構想した。英国流の実地重視の工学教育とヨーロッパの学理重視の工学教育とを組み合わせた構想である。それは「専門職としてのエンジニアの教育」を意図したものであって、顕著な特色が認められる。
第一に、6年間という長期の教育課程を構想し、修業期間を2年ずつに区切り普通・専門・実地の3段階とした。そのうちの専門課程は土木学、機械学、電信学、鉱山学など7学科にも細分化され、専門分野ごとに担当教師を配した。後に造船学が加わって8学科から編成された。
第二に、学理と実地の結合をめざした、サンドイッチシステムという教育方法を採り入れた。最初の2年間は専門基礎科目を学ぶ。3・4年次になると、毎年、6カ月は大学で学習し、あとの6カ月は学生の選択する分野について、学内の施設や付属の赤羽工作分局などで実習をおこなう。最後の2年間は学外の、工部省が所管する灯台、鉱山、鉄道などの官営事業の現場に派遣され実地研修を体験する。これは経験主義的な「英国の教育伝統を重んじつつ、ヨーロッパの教育方法を結び付けた、あたらしい教育実践」として、注目を集めた。しかも施設や設備に特段の配慮をした。実験室、博物室、作業場を活用した教育効果が自覚され、観察・経験・実地が重視されていた。
第三に、エンジニアという専門職の資格認定につながる、実に厳しい試験が絶え間なく繰り返された。週ごと、学期ごとの試験に加え、2年次・4年次修了時の大試験、6年次修了時の成業試験と卒業論文審査に合格してようやく卒業できた。ただし、卒業はできても成績で3段階にふるい分けられ、一等卒業生だけが学士号を授与された。卒業生はほぼ自動的に工部省に任官できたが、学士号の有無によって技手のランクが定められていた。
その一方、幅広い教養教育も重視されていたことが特筆される。「文学、哲学、芸術、さらには自分の専門職に直接役立たないような諸科学にまったく門外漢であったならば、多くの専門職人にみられがちな偏狭、偏見、激情から逃れられない」。エンジニアは専門分野の学力と実務能力だけでは十分でなく、「政治、経済、文化に関する幅広い教育を踏まえて、自らの社会的使命を的確に認識し実現する」ようにと説いて、エンジニアの社会的役割を強調した。工部大学校では士族出身の学生が多く、ともすれば実務を軽視する傾向がみられたし、専門職はとかく思想や行動の偏狭さに陥りがちになるであろうから、この教養教育の重視という観点は大きな意味がある。
このような特色をもった工学教育とその専門部局が大学の中に位置づけられたことは、この頃の世界の大学においては希有のことであった。お雇い教師を送り出した英国では、極東の日本に誕生したあたらしい総合的工科大学であるとの賛辞が送られ、新聞・雑誌で繰り返し取りあげられ紹介された。
当時、欧米では工学部を含み入れた総合的な高等教育機関はまだ設立途上にあった。英国では、1851年と62年のふたつの万国博覧会を機に、学校教育形態での科学技術教育を組織化することが国家的課題であるとの認識がようやく高まり、他国の実情調査が精力的に始められていた。それだけに、大きな関心を集めたのである。日本では、近年、ダイアーのこの教育構想は大学入学式の学長祝辞(京都工芸繊維大学など)の中でも取りあげられている。
なお、ダイアーが先導した工部大学校(とその後身の帝国大学工科大学)からは、日本の工業化をエンジニアとして推進する人材だけでなく、学校の創立・経営・教育に関与して工業化人材の育成にあたる工業教育家も輩出した。彼らの活動にはダイアーの教育観が至るところに表れている。たとえば、京都帝国大学工科大学長となった田邊朔郎は、「社会に尽くしてこそ初めてエンジニアといえる」という教えを心に刻みつけて忘れなかった。琵琶湖疏水事業を企画・遂行したときの工事記録には、5冊ある帳簿のいずれの表紙にも「It is not how much we do, but how well. The will to do, the soul to dare」と筆で書き入れている。私の本志はたくさん仕事をすることではなく、立派に仕上げることである。やる意志、やってみる勇気が大事である、といった意味であろう。ダイアーの生き方がしのばれる箴言である。
エンジニア教育の英国ヘの還元
ダイアーがお雇い教師の任務を終え帰国したころ、英国社会は沈滞気味で諸種の改革が盛んにおこなわれていた。ダイアーも日本体験と日本研究をもとに、改革を提言したり先導したりしたが、主著『大日本』(1904)などに記されているように、日本が改革のモデルになる、とくに日本の国家的教育制度は英国への教訓になると繰り返し説いた。
郷里グラスゴーでグラスゴー・西部スコットランド技術カレッジ(現在のストラスクライド大学)が設立される際には、理事の1人として教学部門を担当した。その際、日本で自身が編集した『工部大学校1879年度要覧』を大いに活用し、『グラスゴー・西部スコットランド技術カレッジ1888年度要覧』などを取りまとめた。
それを見ると、「日本から工部大学校の学科課程を移転させた」ことがはっきり認められる。専門学の学科課程や学科の授業科目の編成のほか、実験室や作業室の整備、サンドイッチ方式の導入、昼間部の学生向けに資格証明書を授与する制度など、工部大学校での構想や実践が移植されている。日本教育が還元されたのである。
国会図書館にはその『1888年度要覧』が1冊架蔵されている。「明治廿一年十一月二十日寄贈H.Dyer」。標題紙には、こんな寄贈印と書き入れが認められる。日本での教育実践の成果を導入したということを、自信をもって報告したかったにちがいない。
グラスゴー留学の提言と支援
日本人エンジニアの教育には、帰国してからも関与した。専門職としてのエンジニアをめざしてグラスゴーの大学に学ぶ日本人留学生の勉学と生活を支援したが、なかでも自身の母校であるグラスゴー大学で日本語資格試験が導入されるとき、これを助力したことが特筆される。
1901(明治34)年に、新入生の福澤三八が、卒業に必要な資格試験の中の外国語選択科目に日本語も認定してほしいと大学に願い出たとき、ダイアーは同試験を管理・監督する委員会に働きかけた。これが功を奏したことで、日本人留学生は大いに便宜が図られることになった。興味深いことに、初代の日本語試験委員は夏目漱石であって、ロンドンに留学していた秋期と春期の2度出題した。それを受験し合格した留学生は、福澤三八、鹿島龍蔵、佐藤恒二、岩根友愛の4氏である。
ちなみに、グラスゴー大学は英国の中でも機械学や造船学の学門中心地であったし、学外の鉄工所や造船所などでの実地研修が奨励されていたので、明治日本からエンジニアをめざす留学生が集まった。明治期だけで渡邊嘉一、後藤牧太ら50名を数える。
彼らのうち14名は同じグラスゴーにあるグラスゴー・西部スコットランド技術カレッジの夜間課程にも学び、専門技術の習得に直結するような実務的な科目を履修している。ダイアーはお雇い教師時代に、日本政府に対し「工学と科学を専攻した第1世代の学生たちを留学させて、グラスゴー大学で勉学をつづけるよう」提言していた。
ダイアーは、日本でも英国でも、日本人エンジニアの育成と飛躍に尽力したのである。
- 現在のページ: 1ページ目
- 1 / 1
加藤詔士(名古屋大学名誉教授)
1947年名古屋市生まれ。名古屋大学教育学部卒。同大学院教育学研究科博士課程修了。教育学博士。神戸商科大学教授、名古屋大学教授、愛知大学教授などを歴任。専門は英国教育史、日英交流史。主な著書に『英国メカニックス・インスティチュート研究』『夏目漱石と蘇格蘭』『西洋世界と日本の近代化』(共編著)など。
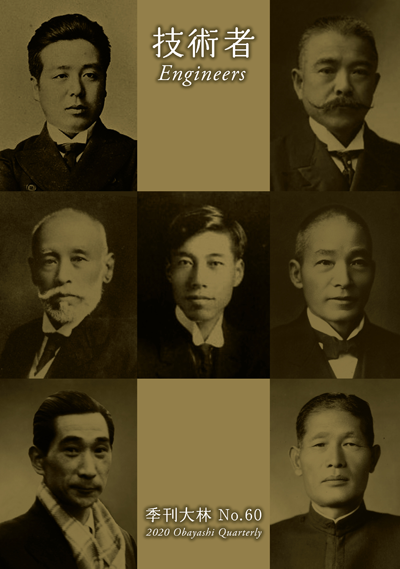
No.60「技術者」
日本の近代化はごく短期間で行われたとしばしば指摘されます。国土づくり(土木)では、それが極めて広域かつ多分野で同時に展開されました。明治政府はこの世界的な大事業を成し遂げるために技術者を養成。その技術者や門下生らが日本の発展に大きな役目を担いました。
今号は、60号の節目を記念し、国土近代化に重要な役割を果たした「技術者」に注目しました。海外で西洋技術を学んだ黎明期から日本の技術を輸出するようになるまで、さまざまな時期における技術者が登場します。
時代を築いたリーダーたちの軌跡を見つめ直すことが、建設、ひいては日本の未来を考える手がかりとなることでしょう。
(2020年発行)
-
座談会:近代土木の開拓者
樺山紘一(東京大学名誉教授、印刷博物館館長)
月尾嘉男(東京大学名誉教授)
藤森照信(東京大学名誉教授、東京都江戸東京博物館館長、建築史家・建築家) - 全編を読む
-
総論:近代土木の技術者群像
北河大次郎
- 全編を読む
-
【古市公威と沖野忠雄】 「明治の国土づくり」の指導者
松浦茂樹
- 全編を読む
-
【ヘンリー・ダイアー】 エンジニア教育の創出
加藤詔士
- 全編を読む
-
【渡邊嘉一】 海外で活躍し最新技術を持ちかえる
三浦基弘
- 全編を読む
-
【田邊朔郎】 卒業設計で京都を救済した技師
月尾嘉男
- 全編を読む
-
【廣井勇】 現場重視と後進の教育
高橋裕
- 全編を読む
-
【工楽松右衛門】 港湾土木の先駆者
工楽善通
- 全編を読む
-
【島安次郎・秀雄・隆】 新幹線に貢献した島家三代:世界へ飛躍した日本のシンカンセン
小野田滋
- 全編を読む
-
【青山士】 万象ニ天意ヲ覚ル者:その高邁な実践倫理
高崎哲郎
- 全編を読む
-
【宮本武之輔】 技術者の地位向上に努めた人々
大淀昇一
- 全編を読む
-
【八田與一】 不毛の大地を台湾最大の緑地に変えた土木技師
古川勝三
- 全編を読む
-
【新渡戸傳・十次郎】 明治以前の大規模開拓プロジェクト
中野渡一耕
- 全編を読む
-
【丹下健三】 海外での日本人建築家の活躍の先駆け
豊川斎赫
- 全編を読む
-
近代土木の開拓者年表


