八田與一(1886-1942)
不毛の大地を台湾最大の緑地に変えた土木技師
古川勝三
恩師、廣井教授の薫陶を受けて土木の新天地、台湾へ
明治政府は日清戦争の勝利によって、1895(明治28)年台湾と澎湖(ほうこ)島を版図(はんと)に入れた。しかし、当時の台湾は、清朝が「化外(けがい)の地」「化外の民」と呼ぶように未開の島であった。全権大使の李鴻章をして「日本はあんな島を手に入れてどうするんだろう」と同情されるような新領土であった。やがて、その同情が現実となって襲いかかって来た。台湾島は、日本の領有に異を唱える土匪(どひ)の反抗、領地への侵入者を許さない原住民族の存在、さらに、漢民族に蔓延する阿片吸引の悪習、マラリア、コレラ、ペスト、アメーバ赤痢等の風土病に侵された島であった。
土匪の討伐や原住民族への理蕃(りばん)政策が最終的に成功するのには、第5代佐久間左馬太(さまた)総督の時代まで、15年の歳月と莫大な国家予算それに多くの犠牲者を要していた。この時以降、治安が良くなるにつれて移民も増え台湾での経済活動も盛んになり、台湾の人口そのものも増えていった。しかし風土病をほぼ駆逐するのには40年、阿片吸引の悪習の終焉には50年近い時間を要している。
日本が朝鮮半島を併合し、台湾の治安が良くなってきた1910(明治43)年に1人の青年が台湾総督府土木部に就職、技手として赴任してきた。八田與一(はったよいち)である。
八田は金沢県今町(現金沢市)の豪農八田屋の五男として生まれた。森本尋常小学校、石川県第一尋常中学校を卒業後、第四高等学校に学んだ。四高では『善の研究』で有名になる西田幾多郎に学び、同級生には正力松太郎や河合良成がいた。数理が得意だった八田は、東京帝大工科大学に入学し、ここで八田に最も影響を及ぼす師と出会うことになる。廣井勇教授である。
1877(明治10)年札幌農学校に2期生として入学した廣井は、第2代教頭のウイリアム・ホイラーに学び、卒業後は自費でアメリカに渡りミシシッピー川の開発工事に従事した後にドイツに留学、28歳にして札幌農学校の教授に迎えられ、北海道庁の技師を兼務、100年以上たった現在も現役の小樽北防波堤を構築し、38歳で東京帝大の教授に迎えられた人物である。廣井の20年に及ぶ大学の研究室からは日本近代土木史に燦然と輝く「廣井山脈」と呼ばれるきら星が輩出している。八田もそのきら星の一人であった。
「八田のような大風呂敷を広げられる人間は、内地に居ては狭量な役人に疎んぜられる」と外地への就職を勧めたのも廣井教授であった。当時、日本が領有していた台湾や朝鮮、それに樺太などは、これから開発が期待される土木の新天地であった。そこで八田は、台湾を選んだのである。八田の人間形成は、真宗王国加賀の「仏の前ではみな平等」という親鸞の教えや西田哲学、それに「橋を架けるなら、人が安心して渡れる橋を架けよ」と指導した廣井の影響が大きかったはずである。
上司、濱野弥四郎技師との出会い
総督府土木部に籍を置いていた八田は、衛生工事を担当することになり大学の先輩である濱野弥四郎技師の下で台南上水道工事に携わることになった。
濱野は東京帝大でお雇い外国人のバルトンから衛生工学を学び、共に台湾に渡って不衛生な台湾の上下水道の構築に携わっていた。恩師であるバルトン亡き後も帰国せず、台湾上水道工事の先駆者として活躍していた。特に、台南上水道は、濱野設計の集大成といえる画期的な施設であった。当時の人口が6万人に満たなかった台南市に対し、10万人分の飲料水を送ることができる急速濾過法を取り入れ、最新設備を備えた大規模浄水システムを造ったのである。水源は曽文渓で、取水塔から水を汲み上げた後、第1ポンプ井戸→取入ポンプ室→沈殿池→濾過器室→第2ポンプ井戸→送出ポンプ室までを山上水源地で行い、続いて南側の浄水場に送られた水は浄水池に溜められ、量水器室を通過して台南市内に送られることになっていた。濱野と八田は水源調査で台南市や曽文渓周辺の調査をくまなく行い、水源地を山上の地へ置くことを決めていた。この調査で、八田は台湾第四の河川・曽文渓から台南にまたがる地形に精通し、水路の引き方や暗渠、開渠をはじめとする水利工事の工法など、多くの知識を濱野から実地に学ぶことができた。八田は、濱野から責任者とはかくあるべきという生き様を学ぶと共に、技術的な技倆や仕事に対する信念をも学んでいる。このことは、後に挑む嘉南大圳(かなんたいしゅう)新設事業の巨大プロジェクトで大いに役に立ったはずである。また濱野自身の人間性にも強く魅かれていく。
「濱野技師は口数少なく温厚で常に謙虚であり、恩師の功績を伝えることはあっても、自らの功績を言うような人ではなかった」と、後日、八田は語っている。
台南上水道工事に携わって2年目、八田は衛生工事担当から発電灌漑工事担当に異動となり、濱野の下を離れるが、台南上水道工事はその後も継続し、10年後の1922(大正11)年に竣工した。山上水源地には八田の提案で濱野の銅像が設置されたが、戦中戦後の混乱で失われた。その後「飲水思源」(「水を飲むときには、井戸を掘った人に想いを寄せよ」という中国の諺)のプレートが埋められた碑が建てられ、後に濱野の銅像も再建された。
試金石、桃園台地の溜池を活用せよ
八田の異動には裏事情があった。その頃、総督府は台湾島内の人口増加に対応するため米の増産が課題となっていた。そこで土木局では水田の適地を探し当て灌漑工事の実施計画を立てていたのである。その適地とは、台北の南西、桃園庁(現桃園市)の高原3万3,000haの大地である。「桃園埤圳(ひしゅう)」と名付けられた灌漑工事は、桃園台地に2万2,000haの完全な良水田を得る目的で企画されていた。これまでに実施された灌漑工事の中で、最大の規模となるはずであった。土木局はこの工事の設計を、八田を中心とする若手技師たちに行わせようと考え、八田の配置換えをしたのである。
桃園埤圳の工事に携わることになった八田は、若い有能な技師と共に山に入り、高原を走り、短期間で基本設計書を作り上げた。この基本設計は、淡水河の上流、石門の地に取水口を設け、約20kmの導水路を造り、この導水路の途中に多数存在する貯水池を結ぶネットワークを構築して、ここから幹線、支線、分線の給水路を通して、河川の水と雨水を利用して灌漑するというもので、いわゆる溜池灌漑方式をとったのである。
この基本計画は総督府で認められ、1916(大正5)年11月には着工された。7カ所の隧道は総延長14.6km、暗渠、開渠数13カ所で総延長5.3km、貯水池数231カ所、水路の総延長に至っては281kmの規模で、竣工までには9年間を要した。総事業費は、770万4,000円余りに上ったが、この完成により、およそ2万2,000haの土地が灌漑され、計画通りの良水田が得られた。しかし、この灌漑工事が官設による最後の工事となり、これ以降、官費官営による灌漑工事は行われなくなった。
桃園埤圳を設計し、工事に携わっていた八田はその業績を認められ、総督府内でも、高く評価されるようになった。八田にとって、桃園埤圳工事は次の工事へと続くスプリングボードであった。もはや「大風呂敷の八田」ではなかった。
余談になるが「埤圳」という言葉は、日本語にはない。「埤(ひ)」とは、農業用の貯水池のことで「圳(しゅう)」とは、その水路を指して言う。「大圳」という言葉は、大正期に造られた造語で、規模の大きな灌漑施設に使われるようになった。
古川勝三(愛媛台湾親善交流会会長)
1944年愛媛県宇和島市生まれ。中学校教諭として教職の道をあゆみ、80年文部省海外派遣教師として、台湾高雄日本人学校で3年間勤務。著書に『台湾の歩んだ道-歴史と原住民族-』『台湾を愛した日本人 八田與一の生涯』(土木学会著作賞)『日本人に知ってほしい「台湾の歴史」』『台湾を愛した日本人Ⅱ』『KANO野球部名監督近藤兵太郎の生涯』など。現在、日台友好のために全国で講演活動をするかたわら『台湾を愛した日本人Ⅲ』で磯永吉について執筆中。
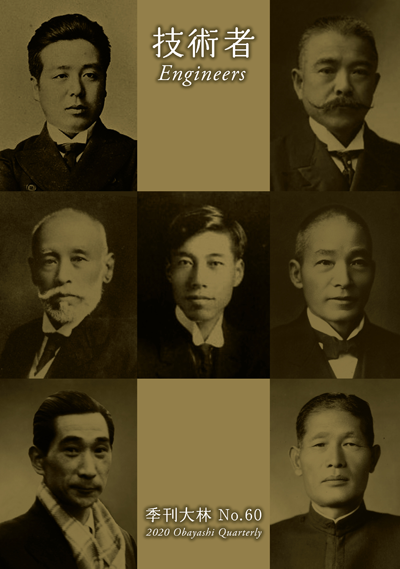
No.60「技術者」
日本の近代化はごく短期間で行われたとしばしば指摘されます。国土づくり(土木)では、それが極めて広域かつ多分野で同時に展開されました。明治政府はこの世界的な大事業を成し遂げるために技術者を養成。その技術者や門下生らが日本の発展に大きな役目を担いました。
今号は、60号の節目を記念し、国土近代化に重要な役割を果たした「技術者」に注目しました。海外で西洋技術を学んだ黎明期から日本の技術を輸出するようになるまで、さまざまな時期における技術者が登場します。
時代を築いたリーダーたちの軌跡を見つめ直すことが、建設、ひいては日本の未来を考える手がかりとなることでしょう。
(2020年発行)
-
座談会:近代土木の開拓者
樺山紘一(東京大学名誉教授、印刷博物館館長)
月尾嘉男(東京大学名誉教授)
藤森照信(東京大学名誉教授、東京都江戸東京博物館館長、建築史家・建築家) - 全編を読む
-
総論:近代土木の技術者群像
北河大次郎
- 全編を読む
-
【古市公威と沖野忠雄】 「明治の国土づくり」の指導者
松浦茂樹
- 全編を読む
-
【ヘンリー・ダイアー】 エンジニア教育の創出
加藤詔士
- 全編を読む
-
【渡邊嘉一】 海外で活躍し最新技術を持ちかえる
三浦基弘
- 全編を読む
-
【田邊朔郎】 卒業設計で京都を救済した技師
月尾嘉男
- 全編を読む
-
【廣井勇】 現場重視と後進の教育
高橋裕
- 全編を読む
-
【工楽松右衛門】 港湾土木の先駆者
工楽善通
- 全編を読む
-
【島安次郎・秀雄・隆】 新幹線に貢献した島家三代:世界へ飛躍した日本のシンカンセン
小野田滋
- 全編を読む
-
【青山士】 万象ニ天意ヲ覚ル者:その高邁な実践倫理
高崎哲郎
- 全編を読む
-
【宮本武之輔】 技術者の地位向上に努めた人々
大淀昇一
- 全編を読む
-
【八田與一】 不毛の大地を台湾最大の緑地に変えた土木技師
古川勝三
- 全編を読む
-
【新渡戸傳・十次郎】 明治以前の大規模開拓プロジェクト
中野渡一耕
- 全編を読む
-
【丹下健三】 海外での日本人建築家の活躍の先駆け
豊川斎赫
- 全編を読む
-
近代土木の開拓者年表


