古市公威(1854-1934)、沖野忠雄(1854-1921)
「明治の国土づくり」の指導者
松浦茂樹
はじめに
明治維新により誕生した新政府は、殖産興業、富国強兵を旗印にして近代化を図っていった。その基盤となるものとして、河川・鉄道・港湾などの社会インフラの整備により国土の近代化を進めていった。それは、「明治の国土づくり」といってよいが、インフラ整備は、民間資本の蓄積が小さかったこともあり、国家が中心となって行われた。
ここでは、「明治の国土づくり」がどのように展開していったのかを概観していくなかで、その指導者として古市公威(こうい)と沖野忠雄の活躍をみていきたい。2人の活躍は後輩たちから高く評価され、2人の還暦祝いとして有志により寄付が募られ高額が集められた。2人は土木学会基金に寄付するとし、それをもとに1914(大正3)年、土木学会が誕生したのである。その初代会長に就いたのは古市であり、2代会長が沖野であった。
フランス留学
1871(明治4)年、明治維新政府の廃藩置県の断行により中央集権国家の体制をつくった後、インフラ整備に乗り出すが、その当初は外国人技術者の雇用により進めていった。彼らはお雇い外国人技師とよばれ、鉄道ではエドモンド・モレルをはじめとするイギリス人技術者、河川・港湾ではファン・ドールン、デ・レーケなどのオランダ人技術者が中心であった。
同時に新政府は欧米に留学生を派遣する。文部省により選抜された東京開成学校(のちの東京大学)の学生12名が1875(明治8)年、アメリカ(9名)、フランス(1名)、ドイツ(2名)に旅立った。工学を専門としたのは4名であり、留学先で土木工学を専攻したのは平井晴二郎、原口要(両人ともアメリカ、帰国後鉄道に従事)そしてフランスに渡った古市公威であった。続いてその翌年、10名が新たに派遣され、沖野忠雄(土木工学)と山口半六(建築学)がフランスに渡った。彼らがフランスに留学したのは、彼らの学んだ外国語がフランス語であったからである。
古市は、まず土木技術者によって創立されたエコール・モンジュに1年間在籍して準備をした後、エコール・サントラルに入学した。サントラルには、1年遅れでやってきた沖野忠雄、山口半六も同年入学となった。彼らは同じ学生ホテルに下宿したが、この下宿には学年が2年上の山田寅吉がいた。彼は小倉藩出身で、1868(明治元)年頃イギリスに留学し、その後、フランスに渡りサントラルで土木工学を学んでいた。
さてエコール・サントラルは、工学を専門とする民間の3年制高等教育機関(後に国有)で、純粋理論のみではなく実務に役立つ知識(理論に基づく応用)を教育するものだった。最初の1年間で工学全体に通じる基礎、後の2年間で専門を習得する内容であった。
古市は、ここを優秀な成績で卒業した後、友人たちと一緒に約20日間にわたる西欧公共事業調査旅行を行った。訪問した国々はイギリス、フランス、ベルギー、オランダで、港湾、鉄道を中心に見て回った。ここで得た知見が帰国後、役立っていった。
サントラルを卒業した古市は、さらにパリ大学理学部に入学した。ここで1年間、数学を中心に学習し、さらに法学部での政治経済学の講義を受けた後、1880(明治13)年帰国の途についた。帰国後は内務省土木局雇となった。
一方、沖野忠雄は卒業後、2年間民間で働いていたと推測されており、1881(明治14)年に帰国した。帰国後、一時、職工学校(現在の東京工業大学)、東京師範学校でも教えたが、84年内務省専任となった。山田寅吉は民間会社で2年程度鉄道建設などの現場を経験したのち79年帰国し、内務省勧農局雇となった。彼らはそれぞれの立場で日本の近代国土づくりに貢献していった。
松浦茂樹(工学博士・建設産業史研究会代表)
1948年埼玉県生まれ。1973年東京大学工学系大学院修士課程修了。専門は国土史学。工学博士。建設省技官(1973年)東洋大学国際地域学部教授(1999年)などを務める。主な著書として『戦前の国土整備政策』『足尾鉱毒事件と渡良瀬川』『利根川近現代史』『遷都と国土経営―古代から近代にいたる国土史』など。
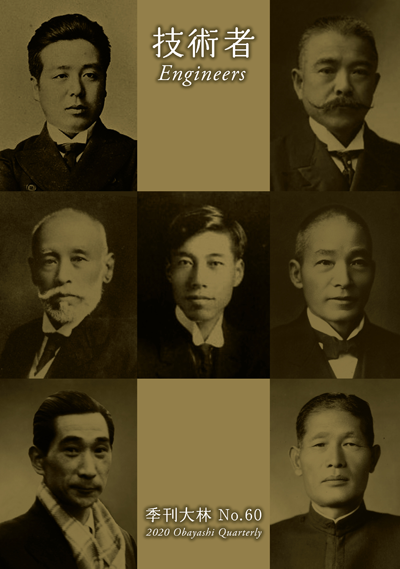
No.60「技術者」
日本の近代化はごく短期間で行われたとしばしば指摘されます。国土づくり(土木)では、それが極めて広域かつ多分野で同時に展開されました。明治政府はこの世界的な大事業を成し遂げるために技術者を養成。その技術者や門下生らが日本の発展に大きな役目を担いました。
今号は、60号の節目を記念し、国土近代化に重要な役割を果たした「技術者」に注目しました。海外で西洋技術を学んだ黎明期から日本の技術を輸出するようになるまで、さまざまな時期における技術者が登場します。
時代を築いたリーダーたちの軌跡を見つめ直すことが、建設、ひいては日本の未来を考える手がかりとなることでしょう。
(2020年発行)
-
座談会:近代土木の開拓者
樺山紘一(東京大学名誉教授、印刷博物館館長)
月尾嘉男(東京大学名誉教授)
藤森照信(東京大学名誉教授、東京都江戸東京博物館館長、建築史家・建築家) - 全編を読む
-
総論:近代土木の技術者群像
北河大次郎
- 全編を読む
-
【古市公威と沖野忠雄】 「明治の国土づくり」の指導者
松浦茂樹
- 全編を読む
-
【ヘンリー・ダイアー】 エンジニア教育の創出
加藤詔士
- 全編を読む
-
【渡邊嘉一】 海外で活躍し最新技術を持ちかえる
三浦基弘
- 全編を読む
-
【田邊朔郎】 卒業設計で京都を救済した技師
月尾嘉男
- 全編を読む
-
【廣井勇】 現場重視と後進の教育
高橋裕
- 全編を読む
-
【工楽松右衛門】 港湾土木の先駆者
工楽善通
- 全編を読む
-
【島安次郎・秀雄・隆】 新幹線に貢献した島家三代:世界へ飛躍した日本のシンカンセン
小野田滋
- 全編を読む
-
【青山士】 万象ニ天意ヲ覚ル者:その高邁な実践倫理
高崎哲郎
- 全編を読む
-
【宮本武之輔】 技術者の地位向上に努めた人々
大淀昇一
- 全編を読む
-
【八田與一】 不毛の大地を台湾最大の緑地に変えた土木技師
古川勝三
- 全編を読む
-
【新渡戸傳・十次郎】 明治以前の大規模開拓プロジェクト
中野渡一耕
- 全編を読む
-
【丹下健三】 海外での日本人建築家の活躍の先駆け
豊川斎赫
- 全編を読む
-
近代土木の開拓者年表


